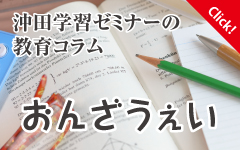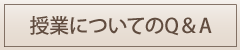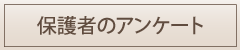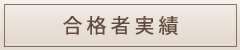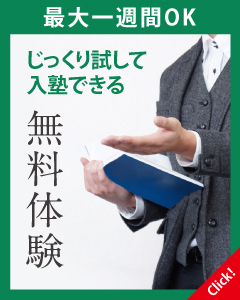振り回されない
その昔、時間の経過を痛切に感じさせてくれる歌がありました。「サザエさん」のエンディングテーマです。この歌が日曜日の夕方にテレビからが流れてくると、子ども心に「あぁ、休日が終わってまた一週間が始まる~」という少し残念な気持ちがわいてきたものです。これが週末に出された課題をまだ片付けていない場合ともなると、もう最悪です! 憂うつな気分で課題消化に取りかからなければなりません(苦笑)。そして時が過ぎ、社会人になった頃には、その歌は「ちびまる子ちゃん」のエンディングテーマに変わっていたことはいうまでもありません(笑)。
個人的には日曜日の夕方にそんな印象があるのですが、現在長野県のある小学校では、日曜日の夕方になると、子どもたちの多くが、月曜日が待ち遠しくてしかたがなくなるといいます。行動分析学者の奥田健次氏が創立した「さやか星小学校」の児童たちです。奥田氏によれば、「日曜日の朝目を覚ますと、『まだ日曜日なの』とため息」「まるで遠足に行く日の前のように、学校に行くのを楽しみにしている」というような声が保護者から聞かされるのだそうです。実はこれにはからくりがあるとのこと。保護者の全面的協力により、家庭ではスマホなどのモバイル端末を一切持たされていないのだそうです。つまり学校でしかデジタル機器をさわれないということなのです。
 奥田氏は近年の日本の子どもを取り巻く問題や事件の背景にあるのは、インターネットであると指摘します。ネットの利用時間が長ければ長いほど、自己肯定感が低くなり、ネット依存になり、ひいては寝不足、情緒不安定の状態を引き起こし、浪費が増えたり衝動性が高くなったりするというのです。もちろん、本来費やすべきことにはエネルギーが注がれないことになります。脳科学者、医師、臨床心理学者など多くの研究者も同様の報告をしています。そう聞くと、何か薬物依存のようにも聞こえてくるわけですが、あながち間違ってはいないように思われます。
奥田氏は近年の日本の子どもを取り巻く問題や事件の背景にあるのは、インターネットであると指摘します。ネットの利用時間が長ければ長いほど、自己肯定感が低くなり、ネット依存になり、ひいては寝不足、情緒不安定の状態を引き起こし、浪費が増えたり衝動性が高くなったりするというのです。もちろん、本来費やすべきことにはエネルギーが注がれないことになります。脳科学者、医師、臨床心理学者など多くの研究者も同様の報告をしています。そう聞くと、何か薬物依存のようにも聞こえてくるわけですが、あながち間違ってはいないように思われます。
iPhoneをつくり出したスティーブ・ジョブズ氏は、自分の子どもにiPhoneを持たせなかったといいます。「あなたは自分の子どもにiPhoneを持たせたいですか。」という質問に対し、「持たせるつもりはない。一度使うと生活から切り離せなくなるように開発したのだから。」と答えたそうです。iPhoneの開発者が依存するようにつくったというのですから間違いありません。子どもたちにとっては、依存性のある薬物と同じわけです。

イネイブラー(Enabler)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。イネイブラーとは、身近な人を心配して良かれと思って行うことが裏目に出て、逆に相手の問題行動を助長してしまう人のことをいいます。アメリカでアルコール依存症について生まれた言葉なのだそうですが、最近では子どものネット依存やゲーム依存についてもいわれるようになりました。たとえばゲーム依存の場合、毎日親が子どもに説教して口げんかになり、挙句の果てにはゲーム機を取り上げ、退屈させないように外に連れ出したり、ゲームをしないことに対する報酬を与えたりします。ゲームをやめない場合も、夜更かしで朝起きられない子どもを起こしてあげたり、学校には「体調が悪い」と連絡を入れてそのまま寝かせておくようなこともします。しかし、自分の問題行動のツケは、必ず自分に降りかかってくるものです。すると、このように親が自分のために様々な世話をしてくれているにもかかわらず逆に親に反発し、自分に起こる不都合なことは「全部親のせいだ」という他責思考になっていくのだというのです。
子どものたちの周りにいる大人が、イネイブラーにならないようにするためには、子どもに振り回されないことです。少子化が進んだ現代は、以前に比べ子どもの要求が優先されることが多くなっているように思われます。しかし、大人が忙しくて子どもにかまっていられなかった昔よりも、働き方改革などのお陰で親の余暇が増え、大人と子どもの距離感が縮まった現代の方が、子どもの不登校や問題行動などの数が多くなっているというのは、なんと皮肉なことでしょう。子どもの気持ちを尊重し、寄り添おうとする気持ちは大切ですが、ときには子どもに寄り添ってはいけない場合もあるということなのでしょう。
子どもたちの周りには魅力的なものがあふれています。生活の中でのルールを決めたり、その中で責任を持たせて行動させ、お互いを尊重できる関係を築いていくことが願われます。

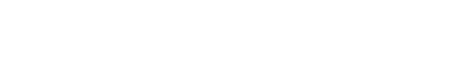
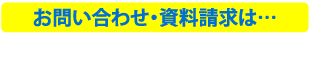
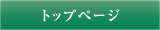
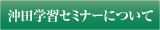
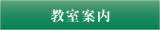
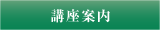
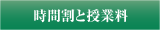
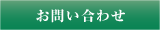
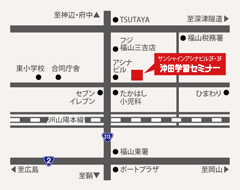 >>>詳しいアクセスマップ
>>>詳しいアクセスマップ