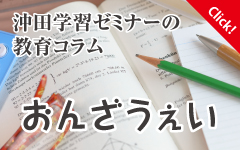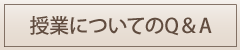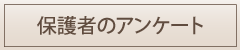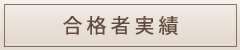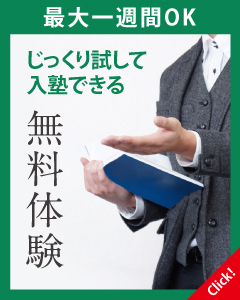野外学習会《古墳探索と火起こし体験~弥生土器で炊飯》
梅雨の真っ只中、降雨の間隙をついて、小6生の野外学習会に『みよし風土記の丘』を訪れました。
まず午前中は古墳探索です。三次盆地は広島県内の古墳の3分の1にあたる3000基余りが密集する地域ですが、ここ『みよし風土記の丘』には、なだらかな30haの丘陵地に、円墳、方墳、前方後円墳、帆立貝形古墳176基が群集しています。なぜこの地にこんなにもたくさんの古墳がつくられたのでしょう。どうしてせまい地域にこんなにも様々な形の古墳がつくられたのでしょう。学芸員さんのお話に耳を傾けながら、いろいろな疑問がわいてきます。これらの古墳の造営には、政権の許可が必要だったと推測されているとのこと。通信手段の乏しい時代にそのような中央集権体制が確立していたというのも不思議です。そしてこの地がユーラシア大陸と政権のあった大和地方の間にあるという地理的な要素からすると、確かに様々な文化や技術が先行して伝えられていたことも十分に考えられそうです。
古墳探索では、古墳の形や作られた位置など、どんな人の墓だと推測されているかなどを聞きながらめぐりました。最大の古墳の頂上まで登ると、見晴らしがよく、周囲の田園風景がとても美しく見えます。途中、森を抜けたところにある古墳が見えると、そこには5・6頭のシカの群れがいるではありませんか!人の気配を感じてすぐに逃げていきましたが、普段はけっして出会えない光景に驚きです。
 |
 |
再現された住居などにも実際に入ってみました。竪穴住居は、予想以上に広い感じで快適そうです。高床倉庫は風通しがよく、外よりも涼しく感じます。柱には『ねずみ返し』があり、ネズミの侵入を防ぐことを目的にしていたことがわかります。ただ、湿気を防ぐためとはいえ、ここまで床を高くする必要があったのかな…と思ってしまいました。
 |
 |
 |
 |
さて、お昼は再現された弥生土器を使っての炊飯です。家からはおかずしか持参していませんので、ちゃんとご飯ができなかったらご飯抜きです。そんなわけで生徒たちは真剣そのもの! 米を研ぐのは普段からやっているとのことで、みんな慣れた手つきです。しかし、炊飯するための火は自分たちで起こさなければなりません。昨今はキャンプブームで、メタルマッチなどという火花を散らせて火を起こす道具もあるようですが、今回は原始的な木と木をこすり合わせる火起こし器です。やはり予想通り(?)の苦戦です。最後は先生の力も借りてやっと発火! でもここからが大事。火吹きの竹筒を使って火種を大きくします。そしてその火を元に焚き火をしてお米の入った土器を加熱していきました。学校や塾の授業では、『ものの燃え方』という理科の単元で、どうやったらよく物が燃えるのかを学習しているのですが、聞いてみると、みんな今までに焚き火をした経験が一度も無いとのこと! 以前にも増して、子どもたちが様々な実体験をする場が失われているのだということを、つくづく感じました。そして楽しみにしていた昼食です。ご飯はふっくらつやつやで、完璧な出来栄えです。普段あまりご飯を食べないという生徒も、おかわりをしてお腹一杯。二つの土器で炊いたご飯をみんなで完食しました。おししい昼食の後は、都道府県カードを使って『地理クイズかるた』をしてくつろぎました。
 |
 |
 |
そして午後からは、ミュージアムの展示品を見学しながら、古代クイズに答えていきました。展示されている石器や矢じり、土器、埴輪、銅鏡や銅鐸…、さまざまな物が長い年月をこえて本物のオーラを放っているように感じます。そんな本物を見たり触れたりする体験は、子どもたちにとって本当に貴重なものだと改めて感じました。

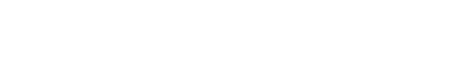
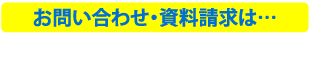
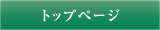
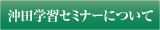
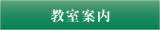
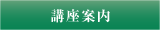
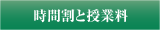
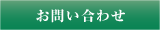
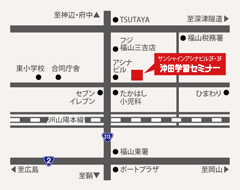 >>>詳しいアクセスマップ
>>>詳しいアクセスマップ