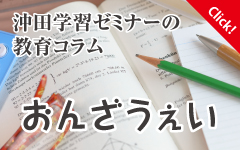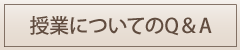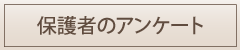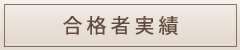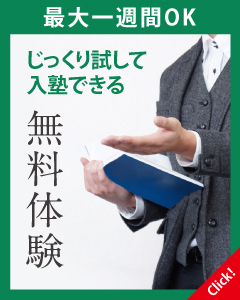「繰り上がり」と「繰り下がり」
算数では計算ミスが少ない子と多い子がいます。計算ミスの多い子は、自然と算数に苦手意識を持ってしまう場合が多くなります。将来の算数・数学への足掛かりとなるという意味でも、計算が正確にできるようになることはとても重要です。
小学生が算数を学び始めて最初の関門となるのは、「繰り上がり」のある足し算です。たとえば8+6の計算を、みなさんはどのように考えますか? おそらく多くの方は、8はあと2で10になるので、6を(2+4)に分けて、8+2+4=10+4=14としたり、あるいは6はあと4で10になるので、8を4と4に分けて4+4+6=4+10=14としたりして答えを出すのではないでしょうか。実際のところは何年も計算するうちに8+6=14だと当たり前のことのように覚え込んでいるのかもしれませんが。
ここで前提となるのは、「10のまとまりになる数の組み合わせのイメージ」をしっかりと持っているということです。今述べたような考え方の過程では、10のまとまりにするために数を分解したり合成したりしています。それこそが十進法のしくみであり、この作業が正確にできるようになることが、計算を正確にできるということにつながります。10のまとまりになる組み合わせのイメージを作るために、おそらく幼児期から繰り返し物を使ってトレーニングしたはずです。算盤(そろばん)を使った計算では、さらに5になる組み合わせも合わせ、常に算盤の玉という具体的な物を動かしながら計算を進めますので、十進法のしくみがイメージしやすくなります。
十進法では常に「10のまとまりになる数の組み合わせ」が大切だと述べましたが、それは1+9、2+8、3+7、4+6、5+5のわずか5つしかありません。ただし、単に数の組み合わせだけでなく、量的なイメージも合わせて覚えることがとりわけ重要です。量的なイメージというのは、実際の物の数や数直線などで視覚的に具体的に考えることで、その感覚がそなわってくるものです。

では、引き算はどうでしょうか。たとえば2桁の引き算37-24を考えると、同じ位同士でそれぞれ引き算をすることができます。十の位は3-2=1、一の位は7-4=3で、37-24=13と簡単にもとめられます。
それでは、42-18はどのように考えますか? 十の位では4から1は引けますが、一の位では2から8が引けません。このような場合は、一つ上の位を含めて計算する「繰り下がり」のある引き算になります。それにはいくつかの方法があります。
まず下の位から引き算を始めます。十の位の4から1借りて10-8=2、元からある2に2を加えて一の位は4であると確定させます。 そして十の位は4から1を融通して3になっているので、3-1=2となり、答えは24となるわけです。このように10から一の位を引いてから、残ったものを足す方法を「減加法」といいます。
また、一の位の2から8のすべては引けませんから、まずは8の内の2を引いておいて、残りの6を十の位の10から引いて一の位は4とし、そして十の位は3-1=2で、答えを24とするという方法もあります。このように引けるものを先に引いておいて、残りを10から引く方法を「減減法」といいます。
そして次のような考え方もできます。42―18の18はあと2でちょうど20になる数です。そこでまず42から20を引いておいて、すると2ほど引き過ぎているのであとで2を足すという方法です。式で書くと、42-20+2=22+2=24となるわけです。
「繰り下がり」のある引き算になると、がぜん子どもたちのミスが出やすくなります。四則計算で一番目の難関が引き算であるといえます。ですからできるようになるまで繰り返しトレーニングが必要です。また前述のように色々な考え方があることが分かると、算数の面白さを感じることにもつながるでしょう。いろいろな考え方を柔軟にできるようになることが理想です。
掛け算は、仕組みの理解よりも、「九九」という歌のようなものを丸暗記してそれをアウトプットすることで行います。桁が大きくなると足し算が増えていくだけです。すべてを正確に覚えていないと意味がありませんから、自信のない人は繰り返し声に出して覚えていくしかありません。
割り算は掛け算と足し算と引き算を総動員して解く計算です。二桁以上の数で割るとき、商を立てることが難関となります。概数の感覚も合わせて見当をつけながら商を立てるには、慣れるしかありません。
大人からすれば、学年が上がるにつれて繰り返し使うなかで計算力は自然に身につくものだと思われがちですが、苦手な子どもからすると、とても大きな悩みの種になっている場合もあります。また、潜在意識から苦手なことを避けようとして、いつのまにか算数・数学という教科を遠ざけてしまう原因にもなりかねません。つまずきがあると感じた場合は早く手当てをして、自信を持って臨める状態にしてあげたいものです。

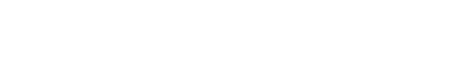
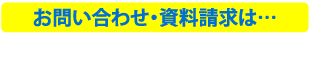
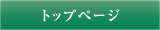
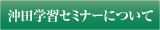
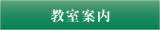
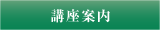
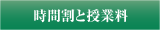
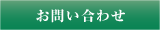
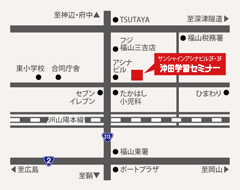 >>>詳しいアクセスマップ
>>>詳しいアクセスマップ