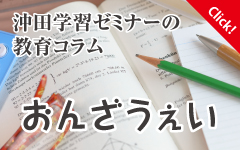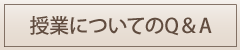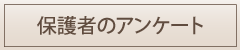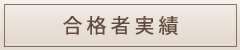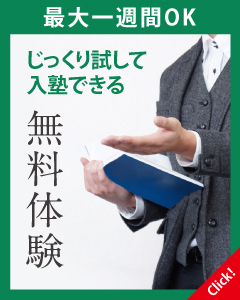理系支援とリベラルアーツ
文部科学省では7月、政府の基金3000億円を活用して大学の理工農系学部を拡充する支援事業について、今春実施の初回公募に申請があった大学や高等専門学校から111校の計118件を選んだと発表しました。デジタルなどの成長分野に対応した学部再編や、人材確保を目指す計画1件につき最大約20億円を支援します。今回の支援を受けて、公立・私立の20大学程度が初めて理系学部を設けるとのこと。
地球温暖化対策やデジタル関連など、今後大きな成長が見込まれる分野が注目される中、日本ではその担い手となる理系学位取得者の割合が他の先進諸国に比べ低いことが指摘されていました。このため政府は理系学生の比率を現在の35%から経済協力開発機構(OECD)加盟国では最高水準の50%程度に引き上げるという目標を設定し、約3000億円の基金を設けて、理系教育の強化を促していくといいます。
日本では明治時代、欧米諸国に追いつくことを目標に人材育成を急ぐ中で、法律がわかる官僚と技術官僚の両方を育成しようとしたところから、「文系」と「理系」の区別ができたのだそうです。そしてその両輪が上手く回転することで、資源の少ない我が国は、加工貿易を中心として経済的な地位を築いてきました。

ところが、バブル経済崩壊以降の日本はデフレや円高が長く続き、国際競争力を維持するために生産拠点を移すなどの合理化を余儀なくされました。文部科学省も合理化を進める中で国立大学の独立法人化などを進め、多くのノーベル賞受賞者を輩出してきた科学分野への基礎研究予算を削減してきました。そのような経緯からすれば、日本の理系分野の地盤沈下も、日本人の給与水準の低迷も至極当然のように思われます。
現在はDX(デジタル・トランス・フォーメーション)が進み、さまざまな分野で本格的なIT化やAI化が図られている真っ只中! 文系・理系の区別なく「理系」の素養が求められるような時代になりつつあります。高校でのプログラミング教育やデータサイエンス教育が導入されていることは、それを端的に物語っています。そして地球温暖化防止や新エネルギー開発など、目の前には喫緊の課題が山積していますから、その分野の最先端を走るスペシャリストの育成も教育界の大きなテーマです。そのような時代に立ち向かうには、専門的な学力や知識だけでなく、分野に関わらず読解力や思考力を持ち、多面的に物事を考え表現する能力、素養を学ぶためのリベラルアーツ教育重視の環境が必要です。文・理の垣根は今後ますます低くなっていくのではないでしょうか。

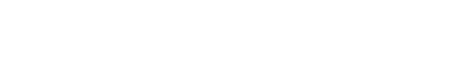
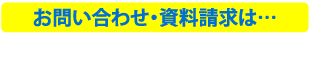
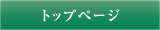
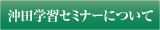
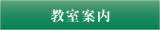
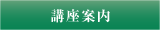
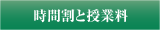
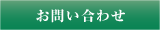
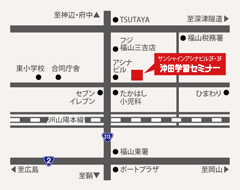 >>>詳しいアクセスマップ
>>>詳しいアクセスマップ